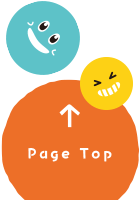【夜尿症】こどものおねしょで悩んでいませんか?夜尿症の原因と家庭でできること、治療法を解説
- 2025年7月3日
- 夜尿症
夜尿症は決して珍しいことではありません。 そして何よりも、お子さん本人のせいでも、ご家族の育て方のせいでもありません。
当クリニックでは、お子様一人ひとりの状況に合わせ、ご家族と一緒に夜尿症と向き合っていくお手伝いをしたいと考えています。
まず知っておきたい「夜尿症(おねしょ)」の基本
夜尿症とは、一般的に「5歳を過ぎても、月に1回以上おねしょをしてしまう状態が3ヶ月以上続くこと」を指します。特に男の子に多く、5歳児では男児の20%、女児の10%が夜尿症と診断されています。多くのお子さんが経験することなので、一人で悩まずにご相談ください。
なぜ夜尿症は起こるの?主な原因を徹底解説
夜尿症の原因は一つだけでなく、いくつかの要因が組み合わさっていることがほとんどです。
- 夜間の尿量が多い: 睡眠中に尿の量をコントロールする「抗利尿ホルモン」の働きが未熟で、夜間に作られる尿の量が多くなってしまうことがあります。
- 膀胱の機能が未熟: 膀胱にためられる尿の量が少なかったり、膀胱が過敏で尿が少し溜まるだけで尿意を感じやすかったりすることがあります。
- 睡眠から目覚めにくい: 膀胱に尿が溜まっていても、その刺激で目が覚めにくい体質のお子さんもいます。
- 便秘: 便秘も夜尿症の大きな原因の一つです。腸に便が溜まることで膀胱が圧迫され、容量が減少したり、膀胱の神経が過敏になったりすることがあります。夜尿症の治療と同時並行で便秘症の治療も非常に重要です。
- 生活習慣や心理的要因、発達の特性: 体の冷え、不規則な生活リズム、心理的なストレスなどが影響することもあります。また、発達障害の特性があるお子さんも夜尿症になりやすいと言われています(ただし、夜尿症だから発達障害である、またはその可能性が疑われるというわけではありません)。

ご家庭でできること:今日から始める夜尿症ケア
夜尿症の治療において、生活習慣の改善が最も重要です。ご家庭では、まず以下の点を試してみてください。焦らず、お子さんのペースに合わせて進めることが大切です。
1. 水分の摂り方を見直す
- 夕食時の水分は適量に: 就寝前の過剰な水分摂取は控えましょう。
- 夕食後から就寝まではコップ1杯程度を目安に: 特にカフェインを含む飲み物(緑茶、紅茶、コーヒー、コールドドリンクなど)は利尿作用があるため控えましょう。
2. 就寝前の習慣
- 寝る前には必ずトイレに行く習慣をつけましょう: 排尿を促し、膀胱を空にする習慣をつけます。
3. 体を冷やさない工夫
- 寝具やパジャマを工夫し、体が冷えないように気をつけましょう: 体が冷えると膀胱が収縮しやすくなり、夜尿の原因となることがあります。
4. 便秘のケア
- バランスの取れた食事や適度な運動を心がけ、便秘を解消しましょう: 便秘は夜尿の原因になります。必要であれば、小児科で相談し、便秘の治療も検討しましょう。
5. 「起こさない・叱らない・焦らない」の三原則
- 夜中に無理に起こしてトイレに連れて行く必要はありません: 深い睡眠を妨げてしまうことがあります。
- おねしょをしても、決して叱らないでください: お子さんはわざとしているわけではありません。プレッシャーは逆効果となり、ストレスでおねしょが悪化することもあります。
- 「いつ治るの?」と焦らず、長い目で見守りましょう。おねしょがなかった日には、たくさん褒めてあげてください。成功体験を積み重ねることが大切です。

平井みらいこどもクリニックでの夜尿症治療
当クリニックでは、まずお子様とご家族から詳しいお話を伺い、その上で、お子様一人ひとりに最適な治療法やサポートをご提案します。
治療の基本
治療の基本は、前述の生活習慣の改善です。それでも改善しない場合に、以下のような治療法を検討します。
1. アラーム療法
夜尿アラームという機器を使い、おねしょをしたら音が鳴って起きる訓練です。夜間の排尿を我慢する力がつくことで、結果的に膀胱にためられる尿量が増えることが期待できます。また、脳に「尿が溜まったら起きる」という感覚を覚えさせることで、根本的な改善を目指します。お子さんとご家族の協力が必要ですが、非常に効果的な治療法の一つです。
2. 薬物療法
夜間の尿量を減らすお薬(抗利尿ホルモン薬)や、膀胱の緊張を和らげるお薬(抗コリン薬)を使うこともあります。お子さんの状態を見ながら、必要最小限の薬で効果が得られるように調整します。
- 抗利尿ホルモン薬(飲み薬): 夜間の尿量を減らすことで、膀胱に溜まる尿の量を減らします。
- 抗コリン薬(飲み薬): 膀胱のサイズを大きくしたり、膀胱の緊張をゆるめる効果があります。膀胱が過敏で頻繁に尿意を感じるお子さんに有効です。
3. その他の治療・併用療法
- 漢方薬(飲み薬): 冷え性などがある場合、補助的に使用することがあります。お子さんの体質に合わせて検討します。
- 便秘治療: 便秘があると夜尿症が悪化することがあるため、便秘がある場合はその治療も並行して行います。適切な排便指導や薬物療法を行います。
最後に、お父さんお母さんへ
夜尿症の治療は、ご家族の理解と協力が不可欠です。お子さんが安心して治療に取り組めるよう、そして何よりも「自分は大丈夫なんだ」と思えるように、私たち平井みらいこどもクリニックも全力でサポートさせていただきます。
夜尿症は、適切な対応と治療で必ず良い方向に向かいます。どんな小さなことでも構いませんので、夜尿症(おねしょ)のことでご心配なことがあれば、いつでも平井みらいこどもクリニックへご相談くださいね。
【参考文献】
- 日本夜尿症学会. 夜尿症診療ガイドライン2021. 診断と治療社.